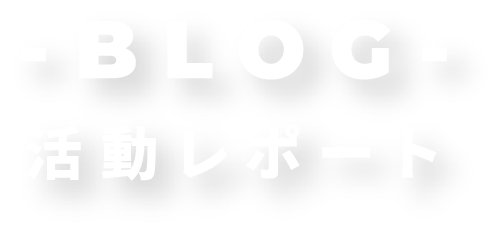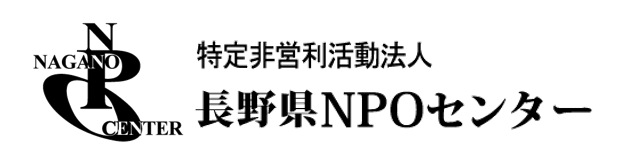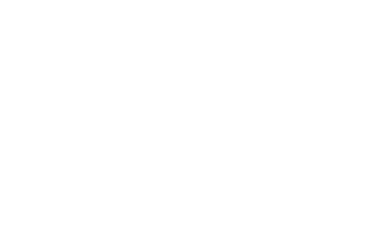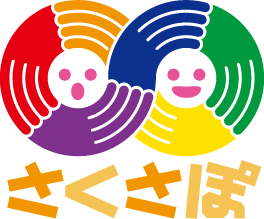8月5日、佐久市役所で行われた「第20回子ども議会」にお邪魔しました。佐久市は、子どもならではの発想に基づいたまちづくりのための要望や意見を聴き、市政推進に役立てるとともに、議会のしくみや運営方法を実際に体験し理解してもらうために、毎年「佐久市子ども議会」を開催しています。
また、第20回目を迎える今年度は、より幅広い世代の声に耳を傾け、多様な視点を取り入れるため、議員として、また、運営メンバーとして新たに高校生枠が設けられました。

当日は、小学校6年生から高校3年生の児童・生徒のみなさんが、計15の提案・質問を行いました。「佐久市の商店街の発展」や「大型商業施設の誘致」などの経済の話、「中学校の施設や通学路、防災」に関わる安全の話、「休憩所・サロンや映画館の設置」などの居場所や文化についての話など、様々なトピックの質問・提案がなされました。
また、2つの高校生チームは「学校の特色ある教育と広報について」と「佐久平地域への人口集中と他の地域の活性化について」という、俯瞰した立場からの質問・提案がありました。

実際に傍聴席で傍聴して感じたことは、「子どもと大人が同じ目線で話そうとする態度」です。子どもたちからは、大人に自分たちの考えを聴いてもらおうと、学級で話し合ったり、学校でアンケートをとったり、高校生チームは実際に集まって話し合ったりなど、それぞれの立場で一生懸命に準備をされてきたそうです。また、質問・提案の内容や原稿を読む姿勢からも「しっかり伝えたい」という様子が伝わってきました。
また、市政のみなさんの視線や相づちを打つ様子などから、子どもたちの訴えに耳を傾けていることがわかりました。特に、市長が、発言している子どもの方に体を向け聴いていたり、答弁をする市長や教育長が、子どもたちに伝わりやすいように、言葉を補いながらお話されたりしたことが印象的でした。
加えて、子どもたちが話す具体的な内容についても「なるほど」と思わされる質疑・提案がたくさんあり、意見の質に年齢は関係がないことがわかりました。
今回「子ども議会」の取材を通して、「子どもの視点を大切にする」ことはもちろん大切ですが、そもそも、それはどういうことなのかを考えさせられました。そして、「子ども議会」がそれを体現している活動の一つだと感じました。また、社会を実際につくっている大人として、子どもの眼差しや発言を受けてどのように振る舞うのかを問われているなと思いました。