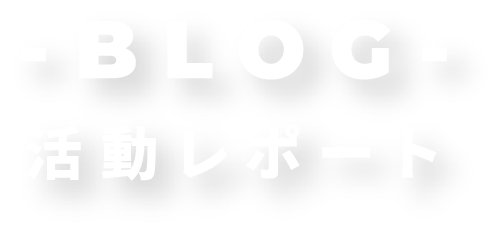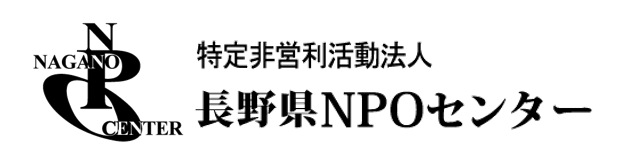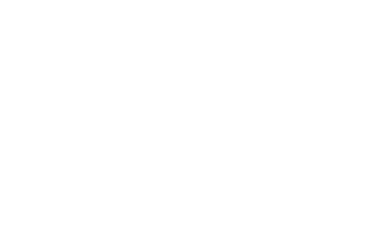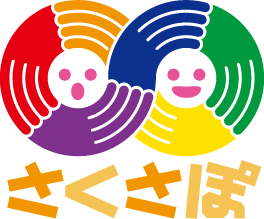野沢北高校の高校生たちが、フードロス問題の解決と食料を必要とする子ども食堂への支援を結びつけるため、2023年秋から探究活動をスタートさせました。
探究活動の始まりとさくさぽのサポート
「みんながお腹いっぱいになるために」というグループ名で活動を始めた野沢北高校2年生たちは、当初、スーパーマーケットへの協力を得ることに難しさを感じていました。そんな時、さくさぽに相談がありました。
そこで、さくさぽのコーディネーターが高校生と地域の農家の方々をつなぎ、直接相談をする機会を設けました。すると、農家の方々も賛同してくださり、JA佐久浅間に協力をしていただけることになりました。
JA佐久浅間本所での農業総会(2024年3月24日)では、高校生たちが「フードロス問題」や「そもそも子ども食堂って何?」についてのプレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションを受けて、農業総会に参加した多くの農家の方々から「毎日商品の回収に来るのが手間だったので始めてほしい」、「古米が大量にある」といった具体的な協力の申し出がありました。
また、「どのような仕組みにすれば農家の方々の負担が少なくなるか」を念頭に置いたアンケートを実施しました。アンケート項目には「子ども食堂」や「フードロス問題」についての項目も含まれていたため、仕組みづくりのアイディアを得ることに加えて、農家の方々が協力できることに気づくきっかけにもなったようです。




2024年春、「みんながお腹いっぱいになるために」の活動は後輩グループ「√coh」(ルート・コウ)へと引き継がれました。(cohは“connect of heart”の略。√は“根っこ”。野菜を作る人、調理をする人、食べる人の心をつなぐ基盤になりたいという思いから「√coh」というグループ名になったそうです)
3年生の先輩から、後輩をさくさぽに紹介したい、こども食堂にも繋いでほしいと希望があり、JAや複数の子ども食堂、そして農家の方々を紹介。関係者間の橋渡し役を担い、情報共有や連携を促進しました。
新旧の学生グループと子ども食堂団体、協力農家が顔を合わせ話し合ったり、それぞれの実践で協力し合ったりすることが、規格外野菜などを活用した食料提供の仕組みづくりへと活動は大きく発展していきました。


実を結んだ地域連携!
そしてついに、「みんながお腹いっぱいになるために」が農家の方々に向けて行ったプレゼンテーションやアンケートが形になります。JAの協力のもと、農家から規格外野菜などを集めるための「寄付コンテナ(回収ボックス)」がJA施設内に設置されることになりました。
この「寄付コンテナ」を利用することで、子ども食堂のスタッフは、農家で廃棄されてしまうはずだった食材を、それぞれの子ども食堂で活用することができるようになりました。
高校生の探究学習の相談から、農家、JA、子ども食堂運営者、コーディネーターといった様々な立場の人々の協働につながり、農家で廃棄されてしまう可能性があった食材が、子ども食堂を通じて子どもたちや地域の人々に届けられる、素晴らしい循環が生まれました。この事例は多機関連携のモデルケースとなりました。
これからの展望 野沢北高「探究活動発表会」より
「√coh」のメンバーは、これからも活動を広げていきたいと、以下の提案や、後輩への活動引継ぎの呼びかけもされていました。
- 子ども食堂同士の連携強化(グループLINEの作成など)
- 子ども食堂の活動をより多くの人に知ってもらうための広報活動の強化
- 児童館や公民館など、子どもたちにとってより身近な場所での子ども食堂開催の検討
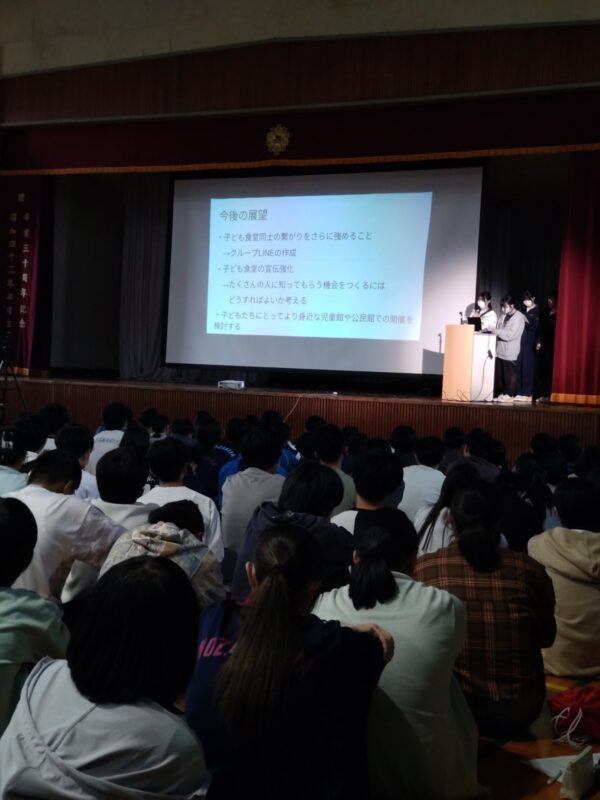
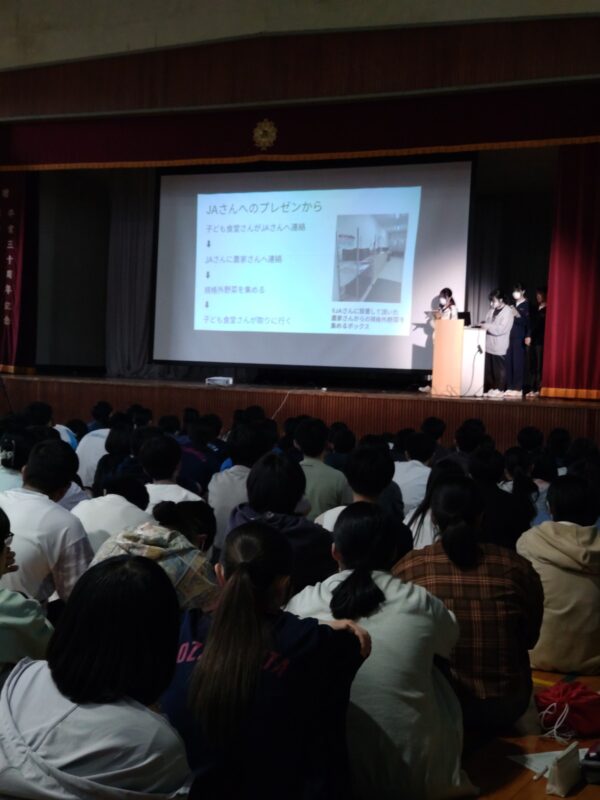
高校生たちの「地域を良くしたい」という想いが、これからも佐久地域に温かい輪を広げてくれることでしょう!