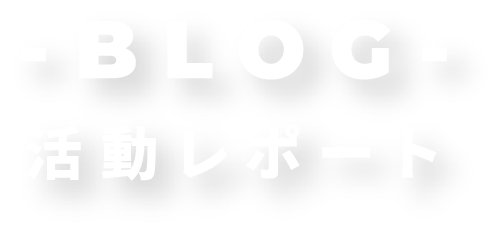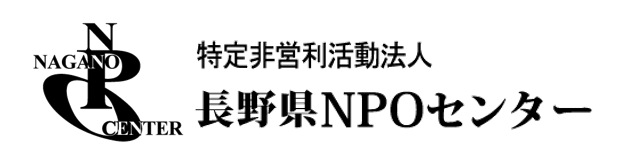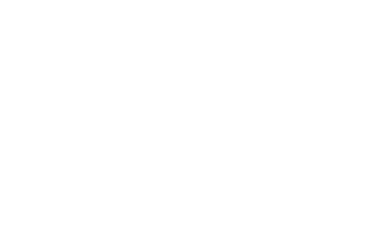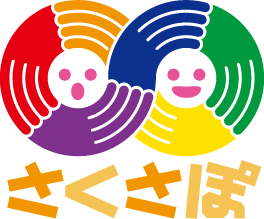8月9日、佐久市総合防災訓練にあわせて、「災害ボランティアセンター開設・運営訓練」と「災害時の多機関連携に向けた情報・意見交換会」が開催されました。
午前の部「災害ボランティアセンター開設・運営訓練」は佐久市社会福祉協議会が主催、午後の部「災害時の多機関連携に向けた情報・意見交換会」は佐久市市民活動サポートセンターが主催しました。

【午前の部:災害ボランティアセンター開設・運営訓練】
一般的に災害時には、被災者を支援したいと駆けつけるボランティアを受け入れるための「災害ボランティアセンター」が、被災市区町村社会福祉協議会により設置されます。
これまで災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練は佐久市社会福祉協議会の職員のみで開催されてきましたが、実際に大規模な災害を想定すると、限られた職員数で通常業務に加えて災害ボランティアセンターの開設・運営を担うことはとても困難です。
それならば多機関の連携を進めることで災害に備えようと、佐久市市民活動サポートセンターの呼びかけにより、今回初めて外部機関(佐久大学・佐久青年会議所・佐久市市民活動サポートセンター)も参画する形で訓練が実施されました。
数か月前から、これまであまり繋がりがなかった各機関を訪問し、趣旨を説明の上で参加協力を呼びかけました。
当日は、佐久市社会福祉協議会のスタッフに加えて、長野県・佐久圏域の他市町村社会福祉協議会のスタッフも応援に駆けつけ、また地球環境高校の学生もボランティア役として参加しました。
本部総務班、ボランティア事業受付班、ボランティア養成受付班、ボランティア派遣調査班、資材班、炊き出し班に分かれて、それぞれの班ごとに訓練を行いました。




今回の佐久市の総合防災訓練での被害想定は、望月地区での地震発生。災害ボランティアセンター立ち上げ訓練では、さらに加えて大雨による浸水被害が発生した想定で訓練を実施しました。
本部には被災した住民や家族、外部からのボランティア希望や物資支援希望など、様々な問合せの電話が次々とかかってきます。いかに情報を可視化して共有しながら対応するか、難しさを体感しました。
電話をかけてくる相手も焦っているため、スムーズに情報を聞き取ることは簡単ではありません。市外から応援に入るスタッフは地名がわからないため、聞き取るのにより時間がかかるという気づきもありました。
次から次へと鳴りやまない電話の問合せに対して、電話対応係と聞き取った内容を情報共有用にまとめる係、2人1組で対応できると良いという提案もありました。
被害が大きかった地域の近くに、災害ボランティアセンターのサテライト(活動の調整を行うボランティアセンターの地域事務所)を設置するかどうかの検討も行われました。
訓練に参加した長野県災害時支援ネットワークの古越武彦さんからは、「災害ボランティアセンターのサテライト設置にあたっては、駐車場の大きさが大事。過去の被災地では、パチンコ施設や葬祭場にサテライトを設置した例もあった。ハザードマップ等で被害が想定される地域において、企業などの民間事業者と行政が、相互に協力し人的・物的支援を行うための協定をあらかじめ結んでいるかどうかが円滑な支援展開の鍵になる」という助言がありました。
アドバイザーとして訓練に参加した長野県社会福祉協議会の山崎博之さんは、「災害にあった時に、声を上げられる被災者はほんの一部。ボランティアセンターのスタッフが被災地域に出向き、潜在的なニーズを聞きにいくアウトリーチの活動が重要です。災害ボランティアセンターは色々な情報が入ってくる入口。福祉的なニーズ(困りごと)を取りこぼさないように」と、ニーズ(困りごと)把握とアウトリーチの重要性について強調されていました。
また、山崎さんからは「例えば被災地域で”学校”という時にどの学校を指すのかなど、地元の人でなければわからないこともある。災害ボランティアセンターの運営に必要な役割のうち、地域外から応援に来る人で担える役割と、地元の人でなければ担えない役割とを意識して整理することが重要」というお話もありました。
各班ごとに振返りを行った後、全員が大会議室に集まり、全体で各班の振返りで出た課題や気づきを共有しました。



【午後の部:災害時の多機関連携に向けた情報・意見交換会】
午後の部では、訓練に参加した各機関のうち災害時の外部連携を担う主担当者に残っていただき、「災害時の多機関連携についての情報・意見交換会」を行いました。佐久市社会福祉協議会、長野県社会福祉協議会、長野県災害時支援ネットワーク、佐久青年会議所、市民活動サポートセンターの職員およびメンバー、佐久大学の教員および学生など15名が参加し、事例発表から学んだり、情報・意見交換を行ったりしました。
冒頭では、各機関の「災害時における役割」、「外部へ協力をお願いしたいこと」、「災害対応における課題」を共有し合いました。災害時におけるそれぞれの機関が持ち合える得意分野やリソース(資源)、課題を考えることで、佐久市における防災対策の課題が見えてきました。また、災害支援の専門性の高いNPOや民間団体の動きを学ぶことで、情報共有の重要性を再確認しました。

事例発表では、長野県災害時支援ネットワークの古越武彦さんより、令和4年の静岡県における台風被害や令和6年1月の能登半島地震における事例から、日本における災害時支援の課題をお話していただきました。
長野県災害時支援ネットワークは、長野県社会福祉協議会、長野県生活協同組合連合会など県内12団体によって構成される長野県域の災害中間支援組織です。ネットワークの事務局を務める特定非営利活動法人長野県NPOセンターは、佐久市市民活動サポートセンターの運営主体でもあります。

古越さんからは、100年経っても変わらない日本の避難所のQOL(生活の質)の低さや、災害時の行政と民間の情報共有等の課題についてお話がありました。
「問い合わせがないからといってニーズがないわけではない。被災者のニーズ(困りごと)の把握や情報共有が適切にされないと、発災後1ヵ月が経っても被災者に支援が届かず、結果的に災害関連死につながりやすくなってしまう。厳しい生活環境におかれている被災者を、地域住民やボランティア・NPOの力でどう支えるか。また状況が悪化した時にいかに迅速に医療・福祉の専門家に繋ぐか。行政と民間で緊密に情報共有をしていくことが、災害関連死を防ぐことにつながる」と話がありました。
古越さんは「行政は量・数で事態を把握するのに対し、民間は質の把握をしている。どちらか片方だけではだめで、それぞれが力を合わせて対策を組むことが重要」と仰っていました。
また、県内他地域での民間連携の先行事例として、「上伊那郡災害時支援ネットワーク」を紹介していただきました。「上伊那郡災害時支援ネットワーク」は地震や風水害など災害が起きた際に、伊那市や駒ヶ根市など8つの自治体からなる上伊那地域の企業などが連携し被災者の支援にあたる事業です。
災害時支援を考えるにあたり、「誰のための取り組みなのか」を明確にしつつ、多機関で協働する大切さを学びました。

午後の部後半は参加者同士で意見交換会を行いました。災害時の情報共有や支援要請について、主に「行政との共有」と「民間での共有」について意見を出し合いました。
意見交換では、社会福祉協議会のみなさんから「行政や民間の方々に情報共有や支援要請を行いたい場面が実際にあったり、今後も想定される。しかし、実際に”誰が、何を、どれくらい行うのか”が曖昧で課題に感じている」と話がありました。
この課題感をきっかけにして、他の自治体の事例を参考にしながら、「情報共有の必要性」や「それを行う場や方法」について、意見を出し合ったり、考えを巡らせたりしました。
また佐久市においては、市の災害対策本部に災害ボランティアセンター本部長が入っておらず、情報共有が難しいという点も課題として挙がりました。被災者に寄り添った支援を行うため、そして災害ボランティアへの二次被害防止のためにも、被災状況やリスク、支援ニーズ等について、行政との間においてより緊密な情報共有が必要という意見も出ました。
特に今年7月に災害対策基本法等の改正法が施行され「福祉サービスの提供」が正式に法に位置づけられたことも受けて、今後ますます行政と民間との情報共有の必要性が高まっています。
意見交換の中では、困りごとに対して民間同士で「実際に協力できる」という話もありました。令和元年の台風19号の際に、佐久大学の学生のみなさんが実際に災害ボランティアをする際に、移動手段の確保が課題の一つだったそうです。その課題に対して、佐久市社会福祉協議会や佐久青年会議所のみなさんによれば「要請があればマイクロバスを出すなどの協力ができる」とのことでした。
いざという時に情報共有が可能な連絡網の準備と、対面での話し合いの機会を通じた信頼関係の構築と、両方の必要性を確認しました。
今回の「災害ボランティアセンター開設・運営訓練、情報・意見交換会」は実際の訓練と意見交換の二本立てで、大変充実した内容となりました。「協働的な災害時支援」の必要性はもちろんですが、それを行うための具体的な方法として、今回のように平時から多機関が連携して取り組む機会・場を継続していく必要性を強く感じました。
準備・運営にあたった佐久市社会福祉協議会の皆さん、そしてお忙しい中ご参加いただいた関係機関の皆さん、ありがとうございました。

※災害ボランティアセンター立上訓練および情報交換会の内容は、後日佐久市社会福祉協議会とともに市の関連部署とも情報共有しました。