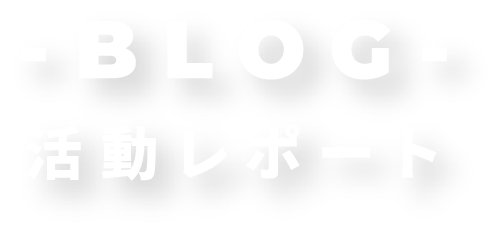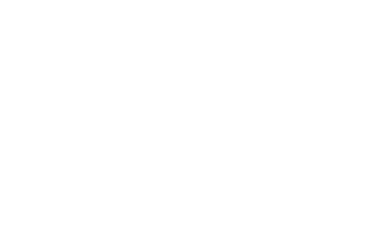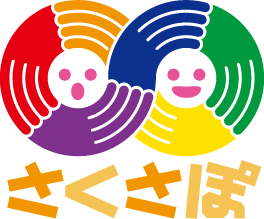6月1日(土)、「牧場に暮らす生きもの「巣まい」大調査 出動!生きもの探検隊」が催されました。このイベントはSAVE JAPANプロジェクト(損保ジャパン株式会社、日本NPOセンター、地域環境団体とNPOが協働して全国各地でいきものが住みやすい環境づくりを行うプロジェクト)の一環として、長野県NPOセンター/生物多様性研究所あーすわーむにより行われました。
当日は、明治20年から始まる神津牧場の歴史を教えていただくことから始まり、牧場内を回りながら、様々な動物の生態を教えていただいたり、人工の巣の設置や観察の方法を教えていただきました。
まず向かったのはムササビの「巣まい」。ムササビの皮や頭部の骨などを見たり触ったりしながら、ムササビの巣の特徴や生態を教えていただきました。驚いたことに、アーボリスト(造園業者や樹木医・林業などにとどまらず、樹木管理に関わる事柄すべての知識を備え実践する職業)の方に実際に巣を設置するところを見せていただきました。



次に向かったのはヤマネの「巣まい」。実際の巣箱や写真を見ながら、麻布大学野生動物学研究室の塚田先生にヤマネの生態について教えていただきました。ヤマネの約6cm~8cmほどの大きさで、巣箱はそのサイズで入ることができて観察ができるように工夫されていました。神津牧場だけで約120個の巣が設置されているそうです。


「次は何の動物かな?」と思ったところで休憩+レクリエーション。クイズ箱の中に手を入れ、ある動物に関係するものを触りながらクイズに答えるゲームです。「競争ではないよ」と言われたものの、子どもたちは目を輝かせながら走り出し、箱の中の角や毛皮、胡桃などを触りながら楽しんでいる様子でした。


最後に向かったのはアナグマの「巣まい」。まず、これまでの巣とは大きさが異なることが驚きでした。こちらでは、同大学院でアナグマの研究をされている柳澤さんに、爪がついたアナグマの皮を見せていただきながら、巣の作り方や特徴、その生態などを教えていただきました。どきどきしながら手を入れてみる場面もあり、巣の深さに参加者は驚いていました。


三つの「巣まい」巡りがひと段落したところで、NPO法人生物多様性研究所あーすわーむの福江さんより、日本の自然環境のお話がありました。「牧場には飼育されている動物以外にも様々な生き物が生息している」、「日本の草原はどんどん減っており、草原性の動物が生きられなくなってきていること」、「様々な環境の維持が大変重要であること」をわかりやすく教えていただきました。

本プログラムは、子どもと大人が一緒に「知る・見る・触れる」を体験できる、大変充実したものでした。また、森の中の樹木の傷や動物の足跡などからお話が膨らんだり、アイボリストの方に質問できたりと、普段学べないことを学ぶことができる大変貴重な機会でした。そして、ここでご紹介できたのは全体の一部であり、書ききれないことがたくさんあります。自分も含めてですが、このようなプログラムを通して、また身近な環境の中で、多くの人に自然に足を踏み入れてほしいなと思いました。